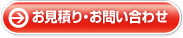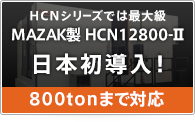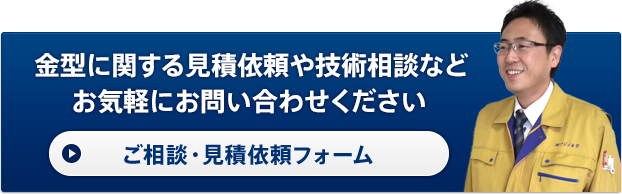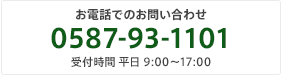「型組図設計」ってどんな作業なんですか?

 お客様から出された仕様書や図面を参考にして、金型の組立図を作図して、設計する作業だよ。参考にする主な仕様は、収縮率や製品形状、製品の取り数、使用される鋳造機の仕様、ゲート位置などだよ。
お客様から出された仕様書や図面を参考にして、金型の組立図を作図して、設計する作業だよ。参考にする主な仕様は、収縮率や製品形状、製品の取り数、使用される鋳造機の仕様、ゲート位置などだよ。

その仕様によって、金型の組立図はどうなるんですか?


それらの情報によって、金型の大きさや構造、使用する材料などが決まってくるよね。
もう少し具体的に言うと、例えばお客様が使用する鋳造機の仕様によって、金型取り付け面をどのようなサイズ、形状にするか、またボルト固定位置なども変わってくるね。
また取り数というのは、何個同時に鋳造して、製品として金型から取り出すかだけど、2個同時取り出しと4個同時取り出しでは当然配置が変わってくるから、アルミが流れる湯道も変わってくる。型組図としても大きく仕様が変わってくるんだよ。


なんか難しそうですね。でもルールや規格のようなものがあって、それに沿ってやれば設計できるんですか?


大体の設計は規格で対応できると思うけど、例えば金型内の製品形状部に溶融したアルミ(湯)を流し込むゲート口の形状や位置なんかは、数値解析ソフトなどによって機械的には設定できるものの、そこに設計者の経験やノウハウなども盛り込んで、最適なゲート設計をすることも多々あるんだ。
ここが金型設計で面白いところの一つで、デジタル思想とアナログ思想の融合ってところかな。
今回のまとめ
ダイカスト金型における型組図設計では、
主に以下のような仕様を決めて型組図に盛り込んでいきます。
主に以下のような仕様を決めて型組図に盛り込んでいきます。
- 使用する鋳造機
- 鋳造機により様々な制約が発生する。そのために鋳造機の仕様は十分に考慮しなければならない。
仕様を間違えると、完成した金型が鋳造機に取り付かなかったりする。また鋳造機ごとに適正な型締力があるので、誤った計算で設計すると型が締まりきらず鋳造できないことが発生する。
その他にも鋳造機仕様によって、金型の厚み、スリーブ形状(湯を流し込む投入口)、押し出し部寸法などが決定されてくる。 - ゲート位置
- 鋳造機から圧入されたアルミ(湯)をその製品のどの場所から圧入するか決定しなければならない。圧入口(ゲート口)が決まると自ずと製品の配置が決まってくる。
ゲート口を正しく設定しないと、湯が製品全体に行き渡らず、鋳巣が出来てしまったりするので、良品率に直結する。 - 冷却配管仕様
- 鋳造すると金型を熱を持ち、それにより製品寸法に狂いが生じる。それを抑制するためには金型の温度調整をするのだが、一般的には冷却水を金型内に流して温度調整する。この配管を冷却配管と呼ぶ。冷却配管は、一般的にユーザーごとによって、仕様が異なるので、事前に十分考慮することが必要である。