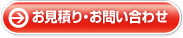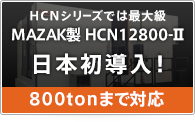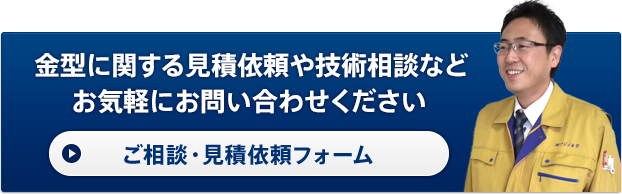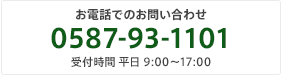2022年11月、本社工場から徒歩5分、愛知県道192号線に面し、トラックでも出入りしやすい場所に念願のフジイ金型第3工場が完成し、本格稼働をはじめました。
そんな折角の機会ですので、この工場建設の意図と今後のフジイ金型の向かう方向について簡単に紹介いたします。
金型の各パーツの生産能力は向上しました
オーダーメイドが基本のダイカスト金型は、人員や設備を増やしても簡単には生産量は増やせません。技術のある人間が連携しながらじっくりと一品一葉で作り上げていくものです。
一方で、技術的な要望は複雑化、高度化してます。これを、今までと同じ人員数で取り組んでいてはリードタイムばかりが延びてしまい、お客さまにお待ちいただく時間が増えてしまいます。フジイ金型としても年間で生産できる台数が減ってしまうという経営的な問題にもなってしまいます。
なんとか従来と同じリードタイムを維持し複雑な構造の金型への対応できないか?そのためにはマンパワーの強化は避けがたく、わずかずつではありますが人員を増やしてきました。もちろん人が増えればその人たちに働いてもらう場所や使ってもらう道具も必要になります。その意味もあって2014年に一宮工場の増設、2017年に第2工場の新設といった増床をおこない、並行して道具となる設備の増強もはかってきました。
これらの活動により、入子(いれこ)や主型(おもがた)などといったダイカスト金型を構成する各パーツの生産体制はかなり強化されたと思っています。
- 一宮工場。右手の建屋が2014年の増設部分
- 第2工場(2017年稼働開始)
組付工程の強化
ダイカスト金型を構成する各パーツの生産工程が終わると、完成した各パーツを組み合わせて検査をする「組付(くみつけ)」とよばれる工程に移ります。
前述したように各パーツの生産能力は向上したのですが、その結果として、後工程となる組付工程の業務量が増え、ここがリードタイム短縮のボトルネックになってきました。今回の第3工場は、まさに、この組付工程の強化、迅速化を意図して建設されたものです。
組付工程は、各パーツを組み立て、期待どおりの鋳造が可能かどうかの検査をおこなう工程です。これだけを書くと簡単そうな工程に思えるかもしれませんが、各パーツには、パーツの生産工程で使用したマシニングセンタなどの切削機械自体に由来する誤差が存在するため、最終的に組み上げた時点での微調整が不可欠です。
しかも「パーツ」とはいってもひとつひとつの重さは1トンを超える重量があります。これを3次元的に組み合わせて全体として隙間のないピッタリとした状態にするのは、ある意味、職人技の世界です。一発で調整が終わることはなかなかなく、組み立てたり、ばらしたりといった作業を繰り返します。
第3工場は、これらの作業を少しでも迅速化できるよう、多くの工夫を取り入れました。建屋の一階全域で室内クレーンを利用できるようにしました。検査に不可欠なダイスポッティングプレスも2台新規導入しました。必要な道具や部材もすぐに使えるよう効率的にレイアウトしたつもりです。検査合格後、迅速に出荷できるよう、建屋内にトラックが乗り入れてクレーンから直接積載できるようにもしました。
- 一階全域で室内クレーンが利用できます
- 安全に作業をするためにもクレーンが不可欠です
- DSP1600
- レイアウトの工夫
環境対応などのためのより複雑な金型への対応
今回の第3工場の完成で、フジイ金型の設計から出荷までの生産体制に関しては一定のレベルに達したと自負しています。この体制を活かして、さらに難易度の高い金型に取り組みます。
自動車メーカーでは、EV車をはじめとする環境対応車への対応のために、さらに複雑な金型を必要としています。他の業界も同様です。これに着実に対応できるようフジイ金型を進化させていきたいとかんがえています。